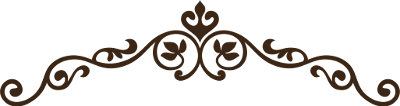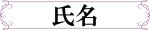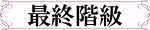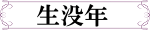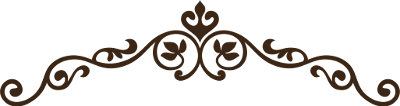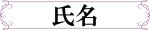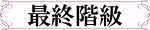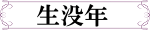|

 土佐藩士 吉松萬彌の長男として土佐国幡多郡中村に誕生する。
土佐藩士 吉松萬彌の長男として土佐国幡多郡中村に誕生する。
父 萬彌は漢学を修め土佐藩では文武館教授、維新後は白川県十二等出仕や天草裁判所長を勤めた人で、茂太郎は幼少の頃より父の開いていた漢学塾で漢学を習い、父にかわって教えるほどであった。
明治3年藩校致道館に入り4年に致道館廃止後、上京し後藤象二郎の書生となり学問に励んだ。

 7年10月 海軍兵学寮に入校し12年9月 練習艦「筑波」に乗組みアメリカ西海岸やカナダ、ハワイを周航し初の海外を体験する。
7年10月 海軍兵学寮に入校し12年9月 練習艦「筑波」に乗組みアメリカ西海岸やカナダ、ハワイを周航し初の海外を体験する。
13年12月 少尉補に任官し「筑波」乗組に補し15年3月より香港、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランドを周航、帰朝後11月 「摂津」乗組に転じる。
16年11月 少尉に進み巡洋艦「浪速」回航の事務取扱員となりイギリスに出張、「浪速」分隊士に補せられ翌年無事帰朝した。
19年7月 参謀本部海軍部第2局課員心得に補し12月 大尉に進級し同第2局課員に、また戦闘方法取調委員の一員として海戦の戦闘方法の研究に取り組んだ。
21年6月、フランス留学を命じられ軍事にとどまらず行政や社会制度の研究も行い、また造兵監督官として兵器製造会社との交渉や兵器試験立会いなどに当たる。
26年5月 帰朝し6月砲艦「大島」分隊長、27年5月 巡洋艦「吉野」分隊長に補せらる。

 日清開戦となると「吉野」は坪井航三の第一遊撃隊の旗艦となり茂太郎も「豊島沖海戦」「黄海海戦」で活躍した。
日清開戦となると「吉野」は坪井航三の第一遊撃隊の旗艦となり茂太郎も「豊島沖海戦」「黄海海戦」で活躍した。
12月 西海艦隊参謀に転じ「扶桑」に乗組みとして威海衛攻略に於いて陸軍輸送、援護射撃、敵艦隊の警戒監視の任にあたり2月 少佐に進級した。
凱旋後、武功調査委員を務め呉鎮守府参謀兼海軍望楼監督官に補せらる。
茂太郎の優れた事務処理能力で、防御計画、出師準備、演習等の計画立案を担当し鎮守府司令長官であった井上良馨の信任厚かった。
30年6月 海軍軍令部第1局局員兼海軍大学校教官に補し12月 中佐に進み海軍軍令部第1局長心得に補せらる。
32年9月 大佐に進み海軍軍令部第1局長に、33年5月 常備艦隊参謀長、7月 佐世保鎮守府参謀長に歴任。
34年7月「浪速」艦長、9月「高砂」艦長を歴任し、伊集院五郎の指揮下「浅間」と共にエドワード七世の戴冠式の記念観艦式に参列しイギリスをはじめ各国の王に拝謁した。
10月 帰朝し36年4月 海軍兵学校教頭兼監に補せらる。

 41年8月 海軍兵学校長に補し中将に進級。
41年8月 海軍兵学校長に補し中将に進級。
43年12月 海軍大学校校長、44年9月 竹敷要港部司令官、同12月 第2艦隊長官を歴任。
大正元年12月 海軍教育本部長に補せらる。
3年3月 シーメンス事件で待命となった松本和の後を受け呉鎮守府司令長官に転じ8月 第一次世界大戦によりドイツに宣戦布告となり所属艦艇の連合艦隊編入、望楼設置、海狭警備にあたった。
4年から戦時編成であった連合艦隊が演習などに際し毎年編成される事となり茂太郎は司令長官を三度も歴任した。
5年12月 海軍大将に昇り、6年12月より軍事参議官を務め9年8月 予備役に編入された。
退役後は海軍有終会長、山内侯爵家商議員、土佐協会顧問、維新資料編纂委員会委員、坂本龍馬・中岡慎太郎
銅像建立建設会会長などを務めた。
京都円山公園に龍馬、慎太郎の銅像が建立された1年後の昭和10年1月2日に逝去、享年75歳であった。
|