|

 維新の動乱の後兵器の発達にともない日本各地の旧藩の城はもはや戦闘の役には立たず、無用の物と思われはじめた。
維新の動乱の後兵器の発達にともない日本各地の旧藩の城はもはや戦闘の役には立たず、無用の物と思われはじめた。
明治6年 太政官による旧藩城の廃棄布達により全国には僅か39の城が存するに至った。
しかし、残った城も補修も行われず腐敗にまかせたため取り壊しの危機に瀕する中、芸術的、築城学的にも極めて価値の高い名古屋城、姫路城を破壊から救ったのが重遠であった。
この二城の価値を認めた重遠は、何としても後世にこの名城をのこさなければと思い、陸軍卿であった山縣有朋にこのみなをしたためた建白書を提出した。
その結果、12年1月29日名古屋城、姫路城とも陸軍の費用で修理することに決定し危うく廃棄をまぬがれた。
名古屋城は大東亜戦争の米軍の空襲により焼失してしまったが(後に再建)、姫路城は戦災を免れ補修を重ねながら昔ながらの偉容を現在もとどめている。
この世界遺産にも登録された姫路城が現存するのはまさに中村重遠の尽力によるものであり、姫路城にはこの事績を記した重遠を顕彰する大記念碑が建立されている。

 姫路城の恩人中村重遠は土佐国幡多郡宿毛村(生誕地碑が建てられている。)の大庄屋 小野弥源次の子にして同村の中村儀平の養子、通称を進一郎と云った。
姫路城の恩人中村重遠は土佐国幡多郡宿毛村(生誕地碑が建てられている。)の大庄屋 小野弥源次の子にして同村の中村儀平の養子、通称を進一郎と云った。
幼少期より講授館に入り三宅大蔵、上村修蔵に学び漢学を修めた。
講授館は文久2年に移転し文館と名を改め読書、習字、算術、作文の四課を設けて教授したが句読役には立田春江(小野義真)、倉田五十馬、そして重遠らがあたり子弟を教育した。
戊辰戦争には最初高知の本藩に従い松山城攻略に参加して後、東征軍に加わり安塚や今市の戦いに参加する。
戦況報告の為に帰郷した重遠は宿毛領主山内氏理に宿毛兵出兵を進言、最初聞き入れられなかったが戦渦の広がりにより氏理の嫡子 陽太郎の出陣が山内容堂に認められる。
この宿毛兵編成の責任者に重遠が任ぜられ「機勢隊」として出陣、庄内藩攻撃に参加し陥落に貢献し戦功により五人扶持を賜った。

 明治2年 軍務官出仕となり3年兵部権大録、大録に進んだ。
明治2年 軍務官出仕となり3年兵部権大録、大録に進んだ。
4年 兵部省七等出仕、5年には陸軍少佐に任ぜられ同年7月には山地元治、野津道貫らと中佐に進んだ(叙従六位)。
6年 正六位に叙し征韓論では土佐出身の将兵が板垣退助と行動を共にし下野していった」が重遠は征韓論反対の急先鋒であったため陸軍に残り12月には熊本鎮台参謀長心得(司令長官は同郷の谷干城)に補せられた。
| 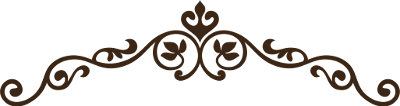

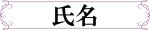
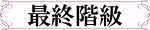
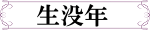
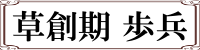



 維新の動乱の後兵器の発達にともない日本各地の旧藩の城はもはや戦闘の役には立たず、無用の物と思われはじめた。
維新の動乱の後兵器の発達にともない日本各地の旧藩の城はもはや戦闘の役には立たず、無用の物と思われはじめた。
